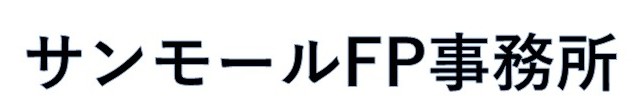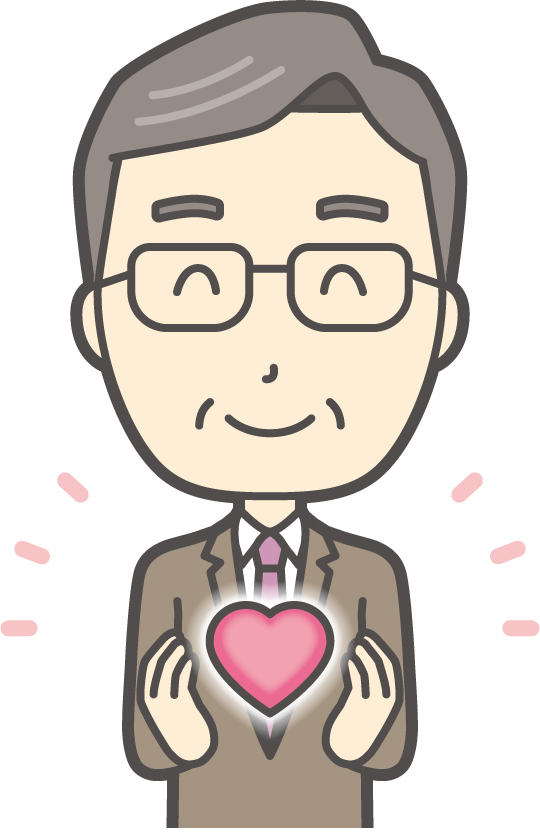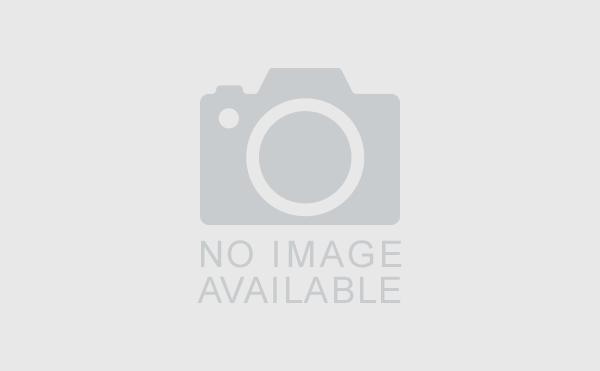手書きじゃなくてもOKに?進む「電子遺言」制度の検討
ご覧いただき、ありがとうございます。
約1週間ぶりのコラム掲載になります。少し間が空いてしまい申し訳ありません。
さて昨日、法制審議会(法務大臣の諮問機関)の民法部会が開かれ、自筆証書遺言に関する新たな制度の「中間試案」がまとめられたとのニュースがありました。
試案はまだ法務省のホームページにアップされていないため、ニュースの内容や公表済みの「試案の案」を見た限りではありますが、この試案では、パソコンやスマートフォンを使って作成する「デジタル遺言書(電子遺言)」を可能とする案が盛り込まれ、注目を集めているようです。
現在、自筆証書遺言はすべて手書きで作成する必要があり、全文・日付・氏名を自分で書き、押印しなければなりません。しかし、特に高齢者や障害者にとっては負担が大きく、書き間違いや書き直しが必要になることも珍しくないといわれています。
また、誤解や争いを避けるために公正証書遺言を選ぶ方もいますが、公証役場に出向く必要があり手続きが煩雑であることや、手数料の負担が生じることがネックとなっていわれています。
こうした状況を受けて、誰でも簡単に、かつ安全に遺言を残せる制度を目指すため、今回の見直しが検討されています。
中間試案によると、デジタル遺言書を認めるためには、一定の条件を満たす必要があります。
たとえば、パソコンで作成した遺言内容を、本人が自ら読み上げ、その様子を録音・録画することや、2人以上の証人(親族以外)の立ち会いを必要とすること、完成した遺言を法務局などの公的機関に提出して保管してもらうことなどが想定されているようです。本人確認についても、顔認証や「振る舞い認証」などの新しい技術の活用も検討されているようで、信頼性をどのように担保するかが今後の焦点のようです。
この中間試案は、今後パブリックコメント(一般からの意見募集)に付されたうえで、2026年ごろを目標に民法の改正が行われる見通しといわれています。制度が実現すれば、時間や場所を問わず、自分の意思を形に残せるようになり、遺言作成のハードルが下がるとされています。
一方で、手軽さが増す分、偽造やなりすましのリスク、第三者による強要といった課題も考えられるといわれ、こうした点についても慎重な議論が必要とされています。
遺言は、自分の人生の最後に大切な人へ思いを伝える大切な手段です。
私自身も、すでに自筆証書遺言を書いて保管しています。
制度の変化に目を向けることは、自分らしい生き方・終え方を考えるうえでの一歩になります。まだ先の話と思わず、関心を持ってみてはいかがでしょうか。